
リレー書簡
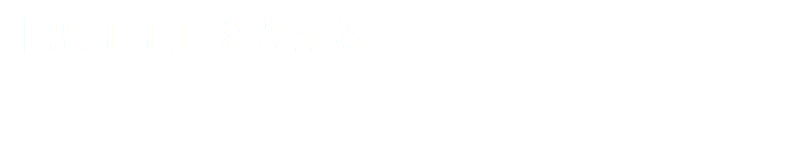
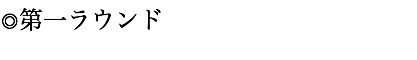
古沢健太郎様
1月10、11日と福島を訪ねてから半年が経とうとしていますが、その後いかがお過ごしですか。
三原由起子さん、玉城入野さんにコーディネイトをお願いして福島へ行くことになったのは、福島(それは父の生まれたところでもあります)は、いまどのような状況にあるのか、この目で一度たしかめたい、そういう気持ちがあってのことでもありますが、ご賛同を得て、浅野言朗、小林レント、玉城入野、 中村剛彦、古沢健太郎、古屋友章、三原由起子、宮尾節子、山本かずこ、岡田の10名で行くことができたことは貴重な経験となりました。
その参加者のなかに古沢さんの名前をみつけたときは、おおと思いました。この「リレー書簡」を、とりあえず1月10、11日の福島行きメンバーで始めようと思いついたとき、ボクの第一信の宛先は古沢さんと決めていました。
福島の浪江町、双葉町を訪ねて深く印象づけられたのは、ここでは時間が停止している(死んでいる)ということでした。2011年3月11日以降、時間が止まったままの富岡町駅舎(これはその後解体されてしまいましたが)、あるいは、田んぼにただ積み重ねられていくフレコンバッグ……などなど。そして、時間は止まったままではあるけれども、その光景の裏ではわれわれの想像を超えた規模で、何事かが動き始めていると実感しないわけにはいかないそのとき、なにかを云おうとしても、コトバは出てきませんでした。いま「コトバは出てきませんでした」と書きましたが、ここが現在の困難地点のひとつだと考えています。3.11がわれわれにもたらしたものはいくつかありますが、茫然自失はそのひとつだと思います。いや、もたらされたもののなかでも決定的なものではないでしょうか。茫然自失とは、つまり思考能力の喪失、放棄ということです。
この福島の風景が、いまわれわれが生活している首都圏の風景と無縁であるとはとても思えませんでした。3.11以降、時間が停止した(かに見える)福島で、いまは目に見えないが確実に生成しつつある時間は、やがて誰の目にも明らかとなるようなかたちで首都圏から日本全土を覆うであろうという予感を捨てきれません。こう考える大きな理由が福島第一原発をめぐる諸状況にあることは云うまでもありません。
最近、いくつか地方都市を訪ねましたが、東京を歩いているだけでは気がつくことができない、いまというものがあると思いました。いま日本はどうなっているのか。それを知るには、東京ではなく、「地方」を歩くのが手っ取り早いのではないか。そんなことまで考えました。
いまボクの机の上には一冊の本が置かれています。『大瀧詠一 Writing & Talking』。908ページという大冊ですが、毎日少しずつ読んでいます。ここに収められた大瀧詠一の「分母分子論」は、日本の近現代詩を、いや、そもそも明治維新以後の日本を考える上でも重要な視座を提示していて、おもしろい。読みながら、いま古沢さんはどんな分母の上にどんな分子を乗せているのだろう……などと考えたりしています。
この本の巻末に、「1963年のアメリカ、2011年の日本。ロックンロール、震災後の社会そして——。」という、亀渕昭信との対談が収録されています。「お母さん方が放射能のことを考えなければならない世の中なんてひどすぎるよ。大瀧さんは岩手のご出身でもあるし、いろいろと辛いこともあるのではないかと思ったんだけど……。」という亀淵の問いに対して、大瀧詠一は次のように答えています。「いや、何もないよ。僕は、いかに3・11の前と同じようにできるかどうかが勝負だと思っているんだ」。これを読んだとき、やはりコトバが出てきませんでした。それは茫然自失とは違う、なにか前に向かって一歩踏み出すことを促すもののようで、これからおまえはどのように生きていくのかと問われているように思いました。
古沢さんのつくる音楽を聴いていると、古沢さんはいろいろなことを考えられているように思います。いま古沢さんは音楽についてどのようなことを考えられているのでしょうか。古沢さんの、my favorite musicについてお聞かせいただければと、この手紙を書きました。
だんだんと暑くなってきましたね。お身体をお大事に。
2015年6月30日 岡田幸文
三原由起子様
自分は言葉を取り扱うのが下手で、話すのも書くのも苦手です。福島にご一緒させていただいた後もうまく感想、というか思いをお話することが出来ないまま半年が経ってしまいました。この機会に三原さんに、と思い筆を執りました。
今回の福島行きのお誘いを受けて、参加することに決めた理由は、震災や原発に対する自身のある種の不感症的な部分に対する疑問があったからです。今も自分たちの生活に影響を与え続けているに違いないにもかかわらず、私はそれらを縁遠いものとして特に顧みることもせずにそのままにしておりました。地震の揺れとその恐怖だけが具体的にリアルなものであり、その後メディアを通してしることとなった被災地の様子は津波にしろ、原発にしろ、大変なことであると思う一方でどうも何か今ひとつ他人事、別世界での出来事であるという感覚がありました。
私は東京で生まれ、東京で育ちました。祖父母も父方母方共に東京に居りましたので、所謂里帰りといったものをしたことがありません。特に旅行に行くこともなく、基本的に東京から出ることない私は遠く離れた地があってそこで人が生活しているということ、さらにいえば「地方」という存在を昔からうまくイメージできない、想像し難いというところがあります。勿論、この貧困な想像力を出自や環境の所為だけには出来ません。しかし一方でそのような自分に対して小さな違和感がずっとあったように思います。その違和感を解消する、というのではなくある意味で自分なりに見極めたいと思い福島行きを決めました。
今回福島を訪れて被災地の一端を目の当たりにしてそこで感じたことは、今の自分の生活の崩壊の「可能性」、そしてそれに対する自身の想像力の欠如でした。東京には原発こそないものの、予想もしなかった何かしらの要因で今自分の住んでいる町があの蛇腹の鉄シャッターで家々が封鎖された町と同じようなものになる日が来るのかもしれない。それは自然災害によるものだけではなく、古滝屋の里 見さんが原発事故を「人災」と呼んだのと同じものによってです。「一寸先は闇」「明日は我が身」などと言ってしまえば簡単なようですが、その簡単なことすら私は想像できていませんでした。今現在の日常の延長ではない未来、何かが決定的に変わってしまった未来に対する自分の想像力の貧しさを知りました。 私事になりますが、今年のはじめ、丁度私たちが福島に行ったすぐ後のことですが、同い年の友人に子供が生まれました。その子にとっては震災も原発事故もすでに起きたこと、として過去のものです。であると同時に最初からそれらの影響下にある世界に生きざるを得ないという意味で一生涯の問題となるでしょう。原発事故に関しては特にそうだと思います。今起きていることは現在生きている私たちの問題であることは当然として、これから生まれてくるであろう子供達にも不可避的に関わります。被災地を巡ったそのあと、岡田さんが「福島(の問題)は今の日本の縮図だ」といったことをお話しされたように思いましたが、だとすれば生まれてくる子供達は、生まれながらあのような世界にいきなり投げ込まれるのと同じです。そう言った意味で、その子達は一人残らず被害者(被災者)であると思います。未来のことは当然ながら誰にもわかりませんし、それはまさに想像するしかありませんが、今後も人が生まれ続けれるのは間違いのないことです。自分から離れた場所にあるもの、今回で言えば地理的に離れた福島のこと、時間的に離れた未だ見ぬ未来(と生まれてくるであろう子供達)のことに如何に想像力を向けられるか。ここまでの流れからは唐突に思われるかもしれませんが、ひいてはフィクションであり、想像力と不可分のものである芸術と今回の体験の接点がそこに見えるように自分は感じました。それはまだぼんやりとしたもので、自分の中で形を成していませんが、今後考えていきたいことの一つです。
私はNASAが録音した「惑星の音」を最近よく聴いています。人によってはつまらないものかもしれませんが、自分はそれを音楽と同じように楽しんでいます。通常では聴くことのできない遠い星の音を、何かしらの技術によって耳にすることができるようにしたものですが、私は音楽を作る上で「聴こえないものを聴こえるようにする」ということを常に考えて曲の形を模索しています。それもまた想像力の技術=art/芸術だと思うのです。私は詩歌に接するようになって日の浅い人間ですが、短歌という形式がなぜあの形をとることになったのか、いつも不思議に思っていました。5そして7という音数の形式とは一体どのような技術、芸術なのか、三原さんに聞いてみたく思っております。
暑さに弱い私は8月を前にして既にへばっておりますが、三原さんもどうぞ、お身体ご自愛下さい。
古沢健太郎
浅野言朗様
お元気でいらっしゃいますか。今年の一月には私のふるさとへご同行くださり、誠にありがとうございました。忘れられるどころか、なかったことになりそうな今、皆さんが関心を持ってくださり、心強かったですし、今も皆さんと共にした時間を思い出します。
私に手紙をくださった古沢健太郎君は、いわき市や双葉郡を訪れたことで、震災や原発事故を自分のこととして考えたり、より具体的な想像力を持つようになったとのこと。閉ざしてしまうのではなく、知ってもらうことの大切さをひしひしと感じています。
古沢君への返事を少々。短歌は五七五七七の定型ですが、感情の流れや余韻によって句またがりになったり、字余り、字足らずになることも多々あります。私は震災後、「やりたいことをやる」ということで、ドラムを習ったことがありました。その時、先生に私の短歌作品を読んでもらうこともあったのですが、先生が「あなたの短歌はリズムがあって、とても心地よいんだよね。声に出して読むとすっと入ってくる。」と、褒めてくれました。ドラムのプロにそう言ってもらえたことが、さらなる作歌への励みになっています。どんなに感情を表現しても、もっともなことを言っても、短歌という詩型は韻律(リズム)がその心をより効果的に伝えてくれるのだと思っています。そのリズムが愛誦性につながり、作品が人々に伝わっていくのではないでしょうか。それは音楽でも言えることですよね。
一月の帰省では、黒いフレコンバッグの山が太平洋と対峙している風景が心に刺さりました。インターネットでそういう風景を見て覚悟はしていたものの、実際に自分のふるさとの浜辺がフレコンバッグで敷き詰められてしまうこと、いえ、浜辺だけではありません。民家の庭や農地だったところや谷間にもたくさんあり、あまりにも悲しい風景でした。また、除染作業や原発で働いている方々の身体も心配です。
浅野さんはクールに受け止めていらっしゃる印象を受けて、「なぜ現場を見ても頭で考えようとするのですか。」と、私がその場で熱くなってしまったこともありました。でも、よくよく考えてみると、それは単なるクールではなく、浅野さんの思慮深さだったのですよね。建築家の浅野さんは特に、人が住めなくなって荒れ果てた家や建物をたくさん見るのは辛かったと思います。
ダークツーリズムや震災遺構という言葉があります。建築家として、また一人の人間として、それらのことはどのようにお考えでしょうか。一月に一緒に訪れた富岡駅のホームも、あの数日後に取り壊され、震災遺構とはなりませんでした。
私の浪江町の実家も日に日に朽ちています。人が住まなくなった家屋にあんなに鼠が台頭してくるとは予想もしませんでした。それでも私の生まれ育った場所であり、いつか取り壊さなくてはならない時が来るのかと思うだけで、苦しくなります。
ダンプカーが国道を駆け抜け、町の様子も日に日に変わっているようです。常磐自動車道の浪江インターチェンジが三月に開通しました。複雑な想いはありますが、またみんなで訪れることができればと願っています。
涼しくなってまいりました。くれぐれもご自愛くださいね。 かしこ
三原由起子より
玉城入野 様
その節は、福島をご案内頂きまして、ありがとうございました。その後、いかがお過ごしでしょうか?
さて、福島で感じたことをお伝えいたしたい、と思うのですが、3.11/東日本大震災を<私>の視点から考えようと思う時、三つの出来事をお話ししたいと思います。ここでは、三原さんにお話し頂いたこともあり、頭で考えて会得される情報的な因果関係ではなくて、なるべく身体的な体験をもとにお話ししてみたいと思います。
一つは、2011年3月11日の、その当日のこと。東日本一帯で大きな揺れがあったので、東京にいた人もそれぞれ多くの経験をしたと思います。揺れた、という身体的な体験、それに続くテレビ等の洪水のような報道、交通機関の停滞など、それぞれの場所でそれぞれの経験をしたと思われ、被害の程度の差こそあれ、多くの人を共通の出来事の中に巻き込んだのだと思います。それは、広い範囲がどこまでも内側であるような大きい事件でした。私は、都内の仕事場で打ち合せに出る準備をしていたのですが、崖の上にある木造の仕事場は、三回、豆腐の上にでもいるかのように、とてもよく揺れました。この崖は崩れるかも知れない、と感じるほどに。そして、その日は、夜まで(あるいは、翌日まで)交通手段や通信手段が麻痺して、打ち合せは自然消滅しました。
次に、その年(2011年)の年末、少々遅ればせながら、津波の被災地に入ったときの光景についてです。仙台から北へと車で、一日かけて北上できるところまで行きましたが、街街によって異なっている、復興の速度。まだ、津波当日のようにえぐれた民家や日常品が散乱したままである地区、瓦礫が残っている地域、津波で横転した建物がそのままの地区、瓦礫の撤去が終わってただただ何もない平坦な更地が広がっている地域、それぞれの状態に違いはあっても、津波の跡はまだありありと残っている、そのような時期でありました。津波の跡、物の散乱した惨状は、暴力的な震災の被害を明快に分かりやすく伝え、身体の奥から衝撃が立ち上ってきました。
三つ目が、今年の1月、福島に案内して頂いた時のこと。津波のように即物的で明快な暴力性を持った被害の光景とは、とても対照的なものでした。放射能は見えるものではなく、立ち入りの規制された人影のない街はとても静かで、穏やかな光景であると誤解するほどのものでした。ある方が言っていたように福島に来ても原子力発電所は遠く感じられて、さらに除染によって刈り払われた荒野は、ただ刈り入れているかのような、あるいは清掃しているかのような、一見すると何がどうなっているか分からない光景です。それは、津波被害が分かりやすいのと比べれば、原因と結果の因果関係や、今起きている現象の意味すらも明示はされていない、時間をかけてゆっくりと朽ちて行くとも思われるような幾層にも暗示された光景のように感じられました。
その時に、自分は、震災という一つの大きい出来事のどの辺りに居たでしょうか? 例えば、今から20年前の阪神淡路大震災の時、私は、建築を学ぶ一人の学生でしたが、それはテレビモニターの向こう側にあって、地球の裏側の出来事と変わらない遠い出来事のように感じていました。つまり、完全に大震災の<外側>に居た、と言えます。
しかし、東日本大震災と<私>との関係はより複雑なものでした。その発生の時から激しい揺れを伴って、私は震災の<内側>に飲み込まれていると感じました。けれども、直後からある期間ずっとテレビ等で流されて来る、最初は津波被害の映像、それに続いて福島の原発の被害状況の報道がありました。それらの、自分が体感した震災とは比べものにならない過酷な状況を見ていると、自分が、少しずつ震災の<外側>へと追いやられて行く感覚がありました。
津波被害を見て車を走らせていた時、そこでは震災の<内側>と<外側>の境界は、とても明快なものに思えました。例えば、同じ海岸縁の街であっても、海の見える崖があれば、その線を境に被害の状況は全く違います。全ての家々が飲み込まれた崖下は災害の<内側>であり、無傷の家が残っている崖の上は<外側>にあるように思えます。津波に関する限り、ある線を境に<内側>と<外側>が明示されているように思われます。
一方、福島を訪ねた時、同行されたある方が言っておられたように、福島に行っても、原子力発電所は小高い丘の向こうに隠されていて、遠さを感じさせました。ここでは、見えない放射能、誰にもはっきりとは分からないその被害の本質にあって、<内側>と<外側>は境界の曖昧な(その濃淡の差異があったとしても)、どこに居ても<内側>でもあり<外側>でもある、とてもとらえどころのない空間に投げ出されたような体感があるものでした。
災害の一つの構図として、その<外側>と<内側>が明示されれば、<外側>から<内側>に対して援助がなされて、<内側>を復興するということが行われます。今回の震災の場合、言い尽くされたことであるかも知れませんが、その境界は極めて曖昧で隠されたものであると思われます。自分は、東日本大震災の<内側>にいるとも言えるし、<外側>にいるとも言えます。
宮城で津波の被災地を見た時の、瓦礫の散乱した暴力的な震災の<中心>を目撃した納得感とは対照的な、福島でのあの奇妙に空虚な体感。放射能濃度の分布に沿って<中心>が設定され、そこから歪みはあるにせよ同心円に近い状態で、警戒区域や避難区域が設定されている、という事前の知識から予想されたものとは全く異なった体験。<中心>に辿り着いたはずなのに、<中心>がどこなのか見えて来ない印象。人影のない、あの時間の止まったような静けさ、<内>と<外>がはっきりとしない中で、自分はどこに立っていたのだろう、と考えることが、自分にとって3.11を考えることなのだと思っています。
とりとめのないお話となってしまいましたが、空間を扱うことを生業としている私にとって、この凹みの中に嵌り込んだような身体感覚は、とても大切な起点であると感じております。ありがとうございました。
最後になりますが、季節の変わり目でございます。ご自愛下さいますよう祈念いたしております。
浅野言朗
宮尾節子さま
たいへんご無沙汰しております。宮尾さんに手紙を書くという行為が、いささかぼくには照れくさく感じます。というのも、初めてお会いしたとき以来、ぼくは宮尾さんの前ではいつも酔っ払っていて(たしか2年ほど前、横浜の酒場のカウンターで偶然隣同士になり、気さくに声をかけてくださったのが初めてお話したときでしたが、そのときもすでに泥酔だった記憶があります)、真面目に手紙を書くのがどうもしっくりこない。ですので、いまも少しお酒を飲みながら書いています。お許しください。
今年の1月10、11日にご一緒した福島の被災地への旅について思い出してみるといろいろなことが心に浮かびますが、ぼくのなかで特に印象的に残っている風景は、実は宮尾さんが厚いコートに身を包みながら、ひとりでずっと写真を撮られている姿でした。他に同行した方々も写真を撮られてましたが、ぼくにとっては宮尾さんが撮っている姿が不思議と「旅の風景」として印象に残っています。
その後、旅から帰った1月末に、宮尾さんにもご出演いただいた「ミッドナイト新春お茶会」で、幾つか宮尾さんが撮られた写真を公開しました。その中からここにランダムに載せてみます。
富岡駅近くの津波被害風景
富岡駅近く
双葉町仮設住宅
双葉町「ダルマ市」
双葉町「ダルマ市」のだるま
購入しただるま
浪江駅
帰還困難地域となった町
関東一帯へ電気を送る送電塔とフレコンバック
いま、宮尾さんが撮ったこれらの写真をぼーっと眺めていて、そうか、と変に腑に落ちることがあります。それは浅野言朗さんが前回書かれた手紙を読んでのことです(なお本来は玉城入野さんへのリレーだったのですが、玉城さんがお仕事のご都合でどうしても時間が取れず、ぼくにバトンタッチとなりました)。
浅野さんは福島の現状を目の当たりにして、それまでに彼自身が感じ取っていた<内側>=<被災者>、<外側>=<支援者>という境界がもはや曖昧になりつつあり、実際に福島第一原子力発電所のすぐ側にいながら、「<中心>に辿り着いたはずなのに、<中心>がどこなのか見えて来ない」と感じられ、旅全体の感想として「奇妙に空虚な体感」と正直に述べられています。
この「奇妙に空虚な体感」という浅野さんの表現はぼく自身の心境を代弁してくれたと思っています。そして浅野さんのいう<内側><外側><中心>という捉え方を、ぼくなりに<個人><社会><権力>というふうに置き換えてみて、さらに「敗北感」に近い思いを感じています。私という<個人>はいかに、<社会>、<権力>に比して虫けらのごとく小なる存在かとあの場で感じたからです。
そんな気持ちを引きずりながら宮尾さんが撮られた写真をいま見ていて、そうか、と思ったのは、この<個人><社会><権力>という関係を、宮尾さんが意識的あるいは無意識的かは分かりませんが、常に体のなかに感じて詩を書き、またこれらの写真を撮られていたのだな、と思ったからです。酔っ払いの早合点かもしれません。でも、あの詩「明日戦争がはじまる」もそうだと思います。日常生活で<個人>が捉えたワンショットが、<社会>そして<権力>へと一気につながっています。そのつながりは、並みの人間では貫通できない巨大な壁を幾つも越えています。宮尾さんのそのブレイクスルーの力はぼくには到底真似ができない。これらの写真からも宮尾さんの「見えないものを見ている」ような大きなパースペクティブを持った視力が伝わってきます。
翻ってみて、ぼくはあの福島への旅からほぼ1年経ち、何者でもない微小なる<個人>の内部を覗きこんでモヤモヤとしています。さきほど「敗北感」と述べましたが、ほとんど「絶望感」に近い。<個人>がもはや消え入りそうな地点にいる気配がします。つい数日前、パリでテロがおきました。フランス政府はこれを<戦争>と定義付け、同盟国も狼煙をあげました。ぼくはさらに「絶望感」を酒で紛らわすしかない。そして老犬と散歩をし、星を眺めることくらいしかできない。
だから、<社会>や<権力>に立ち向かう詩人や作家、芸術家が、いかにしてこの「絶望感」を克服し表現しているのかを知りたい。もともと弱気な性格でもあるのですが(そしてこの「弱気」がぼくが詩を読み、書く根拠でもあるのですが)、宮尾さんには、どうしたら「いま」それほどに強く、ときに軽妙に詩を書いていけるのか聞いてみたい、と酔っ払った勢いで手紙を送ります。
中村剛彦
P.S. そういえば前に、宮尾さんがご自宅でたまたま観ていた映画「ビフォア・サンライズ 恋人たちの距離」のイーサン・ホークにぼくが「似ている!」と連絡をいただきましたが、おそらくイーサン・ホークのことではなく、彼と恋人のジュリー・デルピーに下手くそな即興詩を売りつける、道端で酔っ払っているどうしようもない詩人のことだと思いました。いや、それくらいにはならなければ、と思う今日この頃です。
またお酒の席でお話できるのを心から楽しみにしています。
山本かずこ様
今日は12月31日。大晦日です。ミッドナイトのみなさんと福島に行ってから、早いものでもうすぐ一年になります。いつ頃でしたか、山本かずこさんという同郷の詩人がいることを知りました。そしてお会いしたいなと思っていたら、偶然お会いするご縁が繋がりましたね。同じ職場で机を並べた楽しい時期もありました。詩を先に拝読していたので、実際にお会いして思ったことは「詩の肌理と人の肌理が揃っている」方だなあと感心したことでした。
職場でわたしがちょっとした怪我をした時、何か傷薬を持っていませんかとお尋ねするとこれならとオロナイン軟膏を出してくださいましたね。お借りしたオロナインの甘やかな匂いを嗅いでクリーミィな白い軟膏を傷口に塗りながら「やっぱりかずこさんはオロナインだよなあ、鼻にツンときてヒリッとする塗り心地のメンタムではなくて」と妙に納得したのも覚えています。どこを取ってもかずこさんが出てくる不思議。しっかり仕事をこなされているにも関わらず、かずこさんは「非日常の官能の余韻」で、うっとり日常を生きる人の感じがするのでした。
福島にご一緒したときもそうでした。双葉の仮設住宅の広場で長時間、寒風のなかで催し物を見学しているときも、私なんかは「わあ、寒い!」と風を避けて右往左往していましたが、貴女は風になびく髪を手で押さえて微笑みながら、岡田さんとお二人でいつまでもじっと舞台で繰り広げられる演芸を眺めておられましたね。私たちとは全く違う、人生の文脈に沿って生きておられるようで、この時も不思議な気持ちがしました。
さて、まずは前回の「真夜中(ミッドナイト)のイーサン・ホーク」(笑)こと中村剛彦さんからのお手紙にあった、福島の現状やパリのテロ事件などの危機的状況を踏まえたうえで「<社会>や<権力>に立ち向かう詩人や作家、芸術家が、いかにしてこの「絶望感」を克服し表現しているのかを知りたい。もともと弱気な性格でもあるのですが(そしてこの「弱気」がぼくが詩を読み、書く根拠でもあるのですが)、宮尾さんには、どうしたら「いま」それほどに強く、ときに軽妙に詩を書いていけるのか聞いてみたい」とのご質問に答えねばなりません。かずこさんにもいつだったか久しぶりにお会いした時に、開口一番「あの詩(「明日戦争がはじまる」)はどのような気持ちで書いたのですか?」と聞かれたことが印象に残っています。いつも何事にも少し距離を置いてモナリザのように微笑んでおられる印象が強かったものですから、ちょっと驚いたのです。
中村さんの「そしてこの「弱気」がぼくが詩を読み、書く根拠でもあるのですが」というこの言葉こそが、中村さんの表現者としての存在証明をなしているのだと思われます。そして「表現者は弱者たれ」という中村さんの抗議も矜恃もここに現れている気がしてなりません。「ほとんど「絶望感」に近い。<個人>がもはや消えいりそうな地点にいる気配がします」と中村さんが位置づけされる、個人のこの敗北的、絶望的時代にあって、個人が立ち向かわねばならない<外側><社会><権力>は巨大になりすぎて、今や取りつく島がない。弱者の入る隙間もない、ということなのでしょうか。
わたしはそうではなくて逆に、なら今こそ弱者の真骨頂を見せるときではないかと思うのです。「<権力>に比して虫けらのごとく小なる存在」を作品にすればいいのではないかしらと。もともとこうして書き連ねる文字自体が、巨大な虚無に抗って這い回る虫けらの一群なのではないでしょうか。
なぜそんなにわたしは軽々と書けるか。それについては弱者の自覚がわたしにはないからかもしれませんね。そして対峙する相手も強者だと思っていない。というより、小説家が数々の登場人物を自らのなかに見出して、物語を編み出すように。中村さんの言う<個人><社会><権力>それぞれの役割をわたしの中で設置して、そのそれぞれの役割の自分に向かって書いていくから、交通費も要らず(笑)、敵意もあまり持たずに書ける便利さがあるからかもしれない。先日、青山スパイラルでのトークでゲストの三原由起子さんに「宮尾さんて、出るまで温泉掘るタイプ」と言われましたが、そういうことだと思います。だから、「この<個人><社会><権力>という関係を、宮尾さんが意識的あるいは無意識的かは分かりませんが、常に体のなかに感じて詩を書き、」と中村さんが読み取ってくださったのは、当たりなのだと思います。外に出ないで自分を掘るのですから、自分の体温しか出ない、温泉が温かいのはあたりまえだし(笑)、憎みきれないのも自分だから、敗北感や絶望感にやられないのも、やられたら自分が生きられないからでしょう。
表現者のなせる術は結局、自己救済に過ぎないかもしれません。でも、一人は助かります。そこに「一人助かる」という希望を見出すこともできます。助かった一人が、他者に向かう希望もそこから生まれるのではないでしょうか。アダムのあばら骨がなければイブは生まれて来なかったように。あばら骨を取るためにも自己救済としての表現は、無力ではないと信じたい。
震災後の東北には何度か足を運びましたが、今回は被災地に故郷があり被災地に仲間を持つ、三原さんと現地のお知り合いとの交流のなかに混ぜて頂いたことでぐんと、現状が身近なこととして捉えられた気がします。山のように渦高く積まれていく黒いフレコンバック。「ふるさとは赤」と表現された強制避難区域出身の三原さんのふるさとが、こんどは真っ黒に染まっていく。それはまるで政府の検閲を受けて次つぎ「伏字」にされていく、この地の人々の、この地の草木の、無念の声のように、残酷でした。
かずこさん、わたしたちのくにはよごれました。
かずこさん、わたしたちのふるさとは傷つきました。
かずこさん、よごれて傷ついた土地とひとの心を
ずっと、寒風吹きすさぶなかで佇んで、眺めておられた
かずこさん、あの時あなたの視線の先にあったものを
よかったら、わたしに知らせてくださいませんか。
書いているうちに、年をまたいで新年となりました。
あけましておめでとうございます。本年が
かずこさんにとって、どうぞ素晴らしい年となりますように。
宮尾節子
小林レント様
あなたの年齢の頃、私にとっては「未来」という言葉はとても遠い言葉でした。口にすることもない、遠い遠い言葉で、ほとんど注意を向けたこともありませんでした。「未来」という言葉は、詩を書く人間である生身の私にとっては、ほとんど惹かれることのないものでした。
その「未来」の言葉の存在に気づいて、近づいていったのは私の方からだったか、それとも言葉の方からだったのか。
「詩の雑誌midnight press」において、レントさんや久谷雉さん、元山舞さんたちの登場と時期を同じくして、あるとき、目の前に現れたのが、私にとっての「未来」だったのです。
それまでの私は、そのときそのときを生きるだけで、明日のことは考えなかった。刹那的な詩を書き、刹那的な生き方しかできなかった。その刹那のなかで、母親になった。
その場所が、相馬。福島県の相馬です。私は二度結婚したけれど、二人とも相馬と深い関係があるというのは、出会った後から知ったことでした。
書くということは、思い出すことでもあります。ずっと、封印していたその頃のことを、思い出す(この世での記憶だけでなく、かつて猪苗代湖に向かってたたずんでいた私の一族のことも思い出す。その後、鹿島立ちをして土佐の地を目指したという一族郎党の記憶もまた、折にふれて思い出す)。
ところで一度現れた「未来」は、私のなかで、その後、堰を切ったように氾濫します。「この国の未来は?」「子供たちの未来は?」それまで、冷凍したままだった「未来」という言葉が一気に解け出して流れ出てくるような感じでした。
そして、二〇一一年三月十一日午後二時四十六分、東日本大震災が起こりました。「福島の未来は?」「福島の子供たちの未来は?」「この国の未来は?」……、「未来」が、これでもかこれでもかと押し寄せてくる……。
「私は一五年に来たとき、松林の中の屋敷あとの一つの石の上に腰をおろして、涙をおとしたことがある。幕末の京都で守護職として治安のために働き、しばしばその功を賞せられた家が、のち官軍を敵とすることになり、ついにはこの北国にわずかばかりの封土を与えられてやって来て、落ち着く間もなく帰農することになった。会津へかえった者も多かったし、また北海道にわたった者も多かったが、下北の地に骨をうずめようとした人たちもあって、それらは開墾にしたがったが、ほとんどは失敗して流離の民となり、下北から上北の未開拓の原野に散って細々とした生活をたてることになった。いまでも会津武士の子孫だという家は小川原湖付近には少なからずある。世の中は誠実だけでは生き抜けないものがある。(『私の日本地図 下北半島』宮本常一 同友館刊より)
三月十一日のあと、すぐに読み返したのは宮本常一のこの文章でした。昭和二十一年八月に二度目に訪れた下北半島でで見たこと、聞いたこと、感じたことを書いたものです。
国策に翻弄される会津の人々。またしても……。という思いが私にはありました。
ただ、どんなに翻弄されようと、会津の人々は生き延びて、生き延びて、生き延びた。
「お前たちだけでも生き延びなさい」
理不尽な戊辰戦争においても、そう願って子供たちに「未来」を託した者たち。けっしてあきらめなかった「未来」がそこに在った。残る者、離れる者にとっては、「未来」をあきらめないことこそが、生き延びるためのひと筋の光りだったはず。命綱だったはず。
その苦渋の選択を、その苦痛を私たち日本人一人ひとりがどこまで感じ取り、引き継ぐことができるのか。私自身、それを感じることができますように、それを引き継ぐことができますようにと、願います。
双葉町ダルマ市の青空は、デヴィッド・リンチの映画「ブルー・ベルベット」のオープニングの青空とつづいている。何も起きていない、昼下がり。しかし、本当は起きている昼下がり。ただ、この角度からは、この場所からは見えないだけ。パイプ椅子が並べられている。並べた人には、希望がある。ほんの最近まで、たくさんの人たちで賑わったじゃないの? 二〇一一年の一月も、これくらい、パイプ椅子が必要だったじゃないの? 今年もだから、同じ数だけ並べます。だから、たくさんのパイプ椅子たち。しかし、誰も座ることのない。
演歌歌手の人たちの歌を私はパイプ椅子に座って聴きました。この年、デビューするという女性デュオや、この道何十年というベテラン歌手が舞台に登っては降り、登っては降り。聴衆は、だけどわずか十人足らず(三人のときもありました)。
聴衆が誰もいないからといって、歌手たちは歌うことをやめるのでしょうか? そんなはずはない。歌うことに決まっているのです。歌うことが日常だから、日常にとどまる。これが、仕事だから、仕事に徹する。
だって、ずっと歌ってきたのですもの。いまは、夢を見ているのかもしれない。来年は、また、たくさんの聴衆が集まっているのかもしれない。でも、いまは、そんなことは考えないで、ただ歌うだけ。
私は、そのとき、青空の下にいました。
最初から最後まで、ただ、そこにいる(在る)。何も考えずに、いる(在る)ことに、放心する。これは、実は刹那を生きつづけてきた私の得意分野でもあるのです。ただ、そこにいる(在る)を、つづけているうちに、すべての歌手が歌い終わっていたというのが現実です。ずっと、終わらないなら、その場で何時間でも聴いていたのかもしれません。それは苦痛ではなく、私にとっては、いまを生きる方法でもあるのです。
そして、これが、いただいた宮尾節子さんの問いに対する、私のつたない答えでもあります。私には、青い空と歌う歌手の姿が見えただけなのです。
いまは、とにかく生き延びること。この問いは、現代詩にとっても無縁ではないように感じます。本物を志向する心をあきらめない。いまは、堪える時間かもしれないけれど、「詩の未来」をレントさんたちに託したいと思います。
初めてお会いした頃のレントさんは、まだ十代だったのではないでしょうか。レントさんにとっては、「未来」という言葉はいま、どのあたりに位置しているのでしょうか? かつての私がそうであったように、心惹かれない「未来」という言葉かもしれませんが、あえてうかがってみたい、と思いました。
追伸
宮尾節子様
あなたの変わることのない笑顔、あなたの優しいまなざしは私の大事な大事な宝ものです。
宮尾さん、覚えていますか。かつて、お昼休みに新宿御苑を散歩したことがありましたね。
「これ、かずこさんにあげる」
やわらかい丸みを帯びた石を私にくださいました。
およそ二〇年ほど昔のことでしょうか。
その石を私は大切に持っているのです。
あのときの宮尾さんのあたたかい笑顔と共に、
私はいつでも思い出す。私はいつまでも忘れません。
「これは、宮尾さんにいただいた石……」だと……。
ありがとうございます。
山本かずこ
玉城入野さまへ
ちょうど、閏日という不思議な日付にこのお手紙の多くを綴ることになります。天体の運行と人間的なカレンダーとのあいだのズレのつくった、わずかの余白の日付に。これまで玉城さんと言葉を交わさせていただいたのも、どこか生産的能力においては字余りの、つまりはけっこう酔いの進んだ多弁のとき、計量に失敗した時間においてだったように思います。わたしは、そのようなときの玉城さんの、多くを沈黙におきながらなおも語ってくださる言葉を好きです。
「レントさんにとっては、「未来」という言葉はいま、どのあたりに位置しているのでしょうか?」
山本さんから丁寧にお送りいただいた、この問いとともに過ごしてある先頃からの時間をわたしは貴重なものと思います。拙くともこの問いに応えることから、わたしはわたしの思考らしきものをどうにか象って、差し宛てたく思います。ご案内いただいた福島や、ルービックハウスのお茶会で共に過ごさせていただいた時間には、自己紹介のいとまもありませんでした。そうしたことをするときのなんとなしの気恥ずかしさを、もしかすると玉城さんとはどこかで共有しているかもしれない、そんなわがままな期待のもとに。
わたしなりの読み筋ですが、古沢くん、三原さんのあいだでとりかわされた、実生活に根ざした「故郷」「土地」「現場」の具体的な問題は、浅野さんと中村さんとのあいだで、「<中心>に辿り着いたはずなのに、<中心>がどこなのか見えて来ない」「奇妙に空虚な体感」という、たとえばカフカや、長じてはピンチョンがそれを描き出した近現代の「場所」の体験に接近してゆきます。カフカの『城』やピンチョンの『LAヴァイス』では、さまざまな場所を経巡り人々と出会いながらも、その都度の断片的な出来事が生じるばかりで、さまよう主体のまなざしからは、ことの全景という展望が欠け落ちています。物語の解決にいたる時間らしき時間がありません。
宮尾さんと山本さんとのあいだで、この時間が問題になっているように感じました。表現者がたとえ自己救済しかできないにせよ、「助かった一人が、他者に向かう希望もそこから生まれるのではないでしょうか」という宮尾さんの言葉、「残る者、離れる者にとっては、「未来」をあきらめないことこそが、生き延びるためのひと筋の光りだったはず」という山本さんの言葉。ほとんど絶望的なほど断片化され、それゆえに担われている強さ、最低限だからこそ身のありかたと密接に結びついて生じる強さと思います。人はマントルを隠すかさぶたのような地表にへばりついて生きています。そのわずかな場所の機能が、グローバリゼーションの名のもとに均質化されてゆくなかで、垂直の方向に、もしかすると通じるかもしれない、あるひとつのメールアドレスのように想念される「希望」また「未来」。わたしには山本さんからいただいた「未来」の「位置」についての問いに、ある世代を代表するように綴ることはできません。おそらく適任とはいいかねるわたしの個別性、しかも、ありきたりの個別性から、お応えするほかありません。
「心惹かれない「未来」という言葉かもしれませんが」という留保の言葉に、山本さんのしなやかな弓のようなまなざしを想起します。頭のなかの不鮮明な、しかしたしかにわたしのまなうらにある困難を、射抜かれた感触があります。心惹かれないというよりは、ある種の不和が、この言葉とわたしとのあいだには、長らくつづいています。少なくとも、気安く口にしうるたぐいの言葉ではありません。「原子力、明るい未来のエネルギー」というキャッチコピーもそうですが、小さな頃から、わたしを含めた人間の未来を明るく語ることに違和感がありました。小学生であらかた物心のついたときには、右肩上がりの成長も科学万能時代も終わっていましたから、粛々とツケを返す時が訪れ、わたしも身柄を拘束されつつそれを担うだろうと。
なにごとかを金銭のごとく、未来において返済しうるというその見込みさえ、すぐに都合のよすぎるものと思わざるをえなくなりました。「消費は快楽」という、虚偽意識ですらない文言がどうどうと街中に吊り下げられるなか、学校にもいかずにひきこもった深夜に、イラク空爆のリアルタイム衛星放送を見つづけていたあたりから、個人的なレヴェルを超えでて、不可逆的に加虐者でありつづけるおのれの像が刷り込まれています。いや、むしろ、刷り込まれるという受動態ではなく、わたしにとってはじめて生じつつあった主体性であったかもしれません。もしも、なにかを担うということがありうるとするなら、個人的にも世界史的にも取りかえしがつかない記憶に引き裂かれつづけることではないのか。もちろん世間的に見れば、ねくらのぼんくらの一丁あがりであるのですが。
わたしは性格上、取りかえしがつかないことへの自重で押し黙り、またときおりくずおれるだけで、とりわけ「刹那的」ではない気がしています。少なくとも「刹那的」であることにおいて生き抜く強さを持ちえたためしがありませんし、「いまここ」でさえどこかよそよそしいのです。しかし、漫然と流通している「未来」という言葉とも、やはり親密になれません。自然的な円環において「生き延びる」、ひたすらに物食う者としての暦を断ち切り、石炭、石油、原子力と使役しうる力への精神依存の度合いを発展的に増す社会こそが、爆発的な人口増加と犠牲を伴いつつ、もっとも雄弁に人類の「未来」を口約束してきたのではないでしょうか。現代の日本に生きてきた以上、この言葉をわたしもまた使い殺してきたように思うのです。
「いま」のわたしにとっての「未来」の「位置」を、わたしが一方的に規定するということは、さらなる酷使にその言葉を追いやることであり、「未来」との断絶ばかりを深めてしまうのではないか。このような煩悶に陥りつつ、いまや不気味なものとなり沈黙している、未来にとってのわたしの位置を、手探りせざるをえないのです。「詩の未来」にせよ、次の行に移行するときに、たえず生じてある手探りにおいて求められるほかないでしょう。これは応えとはいえない応えかもしれません。ただ、未だ来たらぬ時、その死角からの逆視線に脅え、さきばしる指先に躊躇をやどすことでしか、自走機械のごとき現在時を、その雄弁を、方向づけることはできない気がしています。脅威を感じることはささいなブレーキのようなものですし、おそらくは未来においてこの時が祝福されることはないでしょうけれど。
「福島の浪江町、双葉町を訪ねて深く印象づけられたのは、ここでは時間が停止している(死んでいる)ということでした」という岡田さんの言葉から、瓦礫のなかに慰霊碑と線量計のならぶ海岸の光景を想起します。残留する放射性物質のゆえに、しばし「人間的な」未来を失い、逆説的に保存されている光景。しかしわたしは、そのときようやく「時間」と向き合っていたのかもしれません。これは言葉にするのが怖いことですが、玉城さん、三原さんに手を振ってお別れした帰りの深夜バスで、古沢くんに「あの光景を、おそらくは美しいと感じた。ただし、それは美しいという言葉でとらえてはならない」と告げたことを記憶しています。それから考えつづけ、また山本さんの問いにいざなわれて、ようやく「時間」に思いあたったのです。つまり、ギャップとしての時間、ブレーキのかかった時間を、わたしは感じていたのかもしれない、と。日常の持続的な慣性が揺らぐこと、うしろまえにひっぱられること、この鮮明な目眩においてわずかに、自走機械の酔いを意識化しうるのではないか。わたしにとって福島での時間は、その圧倒的な沈黙と静止のもとに、せわしなく流れてゆく生活時間よりも「動いている」、いわば「生きた」時間だったのです。
言葉は慣性のなかに宙づりにされている「いまここ」にはない、失われたもの、未だ来たらぬものを喚起します。そこにもやはり目眩がある気がしています。しかし、言葉がいかにして、あるヴィジョンを、そこに息づいている人や草木を喚起しうるのか。とりわけ生にとって切実な記憶、たとえば死者たちのそれを。やみくもに書いてきたわたしには、手だてたる手だてがありません。ただ、死者の声も生まれてくるものたちの声も、手前勝手に「代弁」をしたくはないのです。ほとんど途方もない問いかけかもしれません。しかし、わたしにとって親しみ深い沈黙を、わずかな時間、分かち持たせていただいた玉城さんに、おたずねしたく思うのです。
わたしには知りえぬ苦闘のなかにいらっしゃるかと存じます。やはりわがままな問いになってしまって申し訳ありません。すこしでもご示唆をいただければありがたく。そしてまた、ときおり黙り込みながら語ることのできる時間を、なによりも待ち望んでいます。もしかするとそれが、こうした多弁を恥じいるようにして、わたしの貧弱な身の底からでてくる、未来への種子なのかもしれません。
/小林レント
みなさま
稿を起こす前に、まず、お詫びしなければならないことがあります。
それは、このリレー書簡の第4信において、浅野言朗さんよりお手紙をいただきながら、その時期、のっぴきならない事情があって、どうしてもお返事ができなかったこと、そして、わたしのピンチヒッターを、中村剛彦さんが引き受けてくださったことです。
浅野さん、中村さん、執筆者のみなさん、ミッドナイト・プレス編集部、読者のみなさまには、ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。
また、この度、リレーが一巡した後に、わたしに書く機会を与えてくださった岡田幸文編集長に、心よりお礼申し上げます。
昨年(2015年)1月11、12日に、みなさんと福島に行って、1年以上が経ちました。
あのときのわたしは、妻の三原由起子とともに、コーディネーターの任をおおせつかっていたのですが、気持ちは、どこか受け身であったように思います。というのも、わたし自身は東京の郊外に生まれ育ち、立場としては、浪江町出身である三原の夫というだけで、福島県のこと、浪江町のことを尋ねられても、なにも答えられないのではないかと、ひるむ気持ちが心の中を占めていたのを、いま思い出しています。とはいえ、結婚前から幾度となく訪れた浪江町は、わたしにとっても、大切な場所であることに、変わりありません。
里見喜生さんによるスタディツアーで、富岡、原発のある大熊、双葉、そして浪江といった浜通りの町をめぐり、いわき市の湯本にもどった後、わたしたちは、駅にほど近い居酒屋で、ひとりひとり、今回の福島行の感想を述べ、意見を交わしました。このとき、わたしは、
「無人になった町に住んでいた人たちは、どこに行ってしまったのだろう。その人たちの生活は、どこに行ってしまったのだろう」
というようなことを言ったように覚えています。「○×で避難生活をしています」とか、「△□でお店を再開しました」といった、実際のことを知りたいわけではありません。また、避難を強いられる以前の生活が良くて、それ以後の生活が悪いと言いたいのでもありません。ある日、突然、その場所で営まれていた人々の生活が消え去る、ということが、どういうことなのか。実景を見たことにより、そんな問いが、口をついて出てきたのだと思います。この問いに、はっきりした答えなどないことは、よく分かっています。しかし、思えば、原発事故以後、わたしは、ずっと、このことを問いつづけ、考えつづけてきたような気がします。
だいぶ、酔いもまわってきた頃だったでしょうか。どなたと、どんな話をしていたのか、いま思い出せないのですが、わたしは、
「震災以前の町、その町での生活を、再現(リプレゼンテーション)するのではなく、現前(プレゼンテーション)させることができるのではないか。それがどんな方法で、どんな表現でかは分からないけど」
と言いました。すると、小林レントさんが「分かるような気がします」と共感を示してくださったように思います(記憶違いだったら、ごめんなさい)。わたしは、酔った勢いで、こんなことを言ったのではありません。先の問いかけとともに、折にふれて、考えてきたことなのです。
映画や写真、演劇、小説等々で、かつての町の様子や、人々の暮らしぶりを〈再現〉することは、それほど難しいことではないでしょう。しかし、〈現前〉させるには、どんな表現方法がふさわしいのでしょうか。それに、そもそも〈現前〉させるとは、どういうことなのでしょうか。わたしが思い浮かべる〈現前〉とは、文学に限っていうと、たとえば、ある詩や短歌、文章の一節などを読んだとき(読むたびに)、その風景や人々が、模写や複製ではなく、そのものとして、目の前にありありと立ち上がってくるような現象です。それは、結局のところ、表現としては、〈再現〉に過ぎないのかもしれません。ただ、うまく説明はできないのですが、単に再現されただけの表現と、現前をかなえる表現とは、まったく別物だと思っています。
こういったことは、被災地の復興や、被災された方々に、直接、なにかの役に立つわけではありません。しかし、震災以後の、文学や音楽といった、あらゆる芸術を考えていく上で、この〈現前〉ということに、なにか手がかりがあるのではないかと、わたしは、思っているのです。
玉城入野
第1信
岡田幸文(ミッドナイト・プレス編集長)→古沢健太郎(音楽家)
2015.6.30
第2信
古沢健太郎(音楽家)
→三原由起子(歌人)
2015.8.1
第3信
三原由起子(歌人)
→浅野言朗(詩人・建築家)
2015.9.1
第5信
中村剛彦(詩人・ミッドナイト・プレス副編集長)
→宮尾節子(詩人)
2015.11.18
第6信
宮尾節子(詩人)
→山本かずこ(詩人)
2016.1.1
第7信
山本かずこ(詩人)
→小林レント(詩人)
2016.2.1

© 詩の出版社 midnight press All rights reserved.